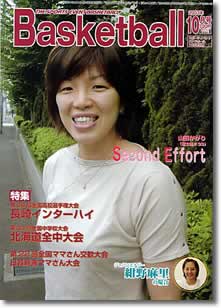
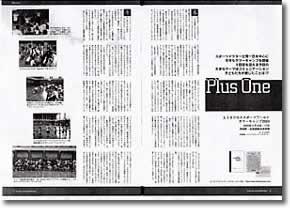
3回目を迎える今回の大きなテーマはコミュニケーション
子どもたちが感じたことは!?
本誌のMY TEAMのコーナーにも登場したことのあるチームエミネクロススポーツ塾の塾長であり、スポーツドクターの辻秀一氏が中心となり“理念共有型スポーツクラブ・エミネスポーツワールド”のサマーキャンプが開催された。
このキャンプは2001年から開催されており、今年で3回目だ。
理念共有型スポーツクラプってなんのこと?とお思いでしょう。
最近では、文都科学省が提唱している“総合型地域スポーツクラプ”という言薬から派生して、地域密着型スポーツクラプとか、地城総合型スポーツクラプなどという言い方をよく耳にする。“エミネスボーツワールド”は、それらと区別するために“理念共有型”と謳っているのだ。
では具体的にどのようなものかというと、辻氏の最大のミッションは「スポーツの社会的価値の創造」であり、日本におけるスポーツの文化としての価値を持たせることである。
「現在の日本でのスポーツの印象はというと、体育会系、勝利至上主義、根性などとあまリ良いものではありません。例えば、勝つためにはどんな手段をしてでも鍛え上げるなどといったように、強化と普及がまったく分かれてしまっている現状をよく目にします」と辻氏は言う。
辻氏の説く「スポーツの社会的価値」とは、『スポーツは医療であり、芸術であり、コミュニケーションであり、教育である』ということ。くだいて言えば、全ての人がスポーツを通じて元気になり、感動し、全てのバリアフリーを感じ、成長するということである。
つまり“理念共有型”とは、そういった考え方を共有するということだ。
辻氏は、ライフスキルというキーワードをもってスポーツの社会的価値を創造できれば、スポーツは魅カあるものになり、普及としての意味も生まれてくる。更には勝つため、強化のための解決策に繋がると考えている。
ライフスキルとは、「より良く生きる術」である。スポーツをするということは、ライフスキルを学び身につけることであり、これが身につけば、社会に出ても役に立ち、自分らしい生活ができるというのがスポーツの価値をライフスキルに見いだした考え方だ。
こうした考え方は、アメリカのPGA(アメリカプロゴルフ協会)やNFL(アメリカフットボールリーグ)がゴルフ・アメリカンフットボールをすることの社会的価値を“ライフスキルの獲得”と捉えているくらい、実際スポーツ現場でも認識されているのだ。
現在、エミネスポーツワールドは4つの部門で構成されている。
1.『チームエミネクロス・スポーツ塾/B・B&チアリーディング』小学1年から中学3年生までの子どもたちと親を対象とし、スポーツの教育性を重視して学んでいく
2.『エミネクラプ』誰もが参加でき、コミュニケーションを大事にしながらB・Bを楽しむ
3.『エクセレンス』ライフスキル(社会力)を重視し、感動をプレーで生み出すと共に、子どもたちのロールモデルを目指すトップチーム(2002年度オールジャパン関東予選準優勝)
4.『No Excuse』スポーツで心身ともに元気に成長し全日本総理大臣杯で優勝を目指す車椅子B・Bチームそこに今年度から、耳の不自由な人たちのB・Bチーム『Rough』が加わって、更には手伝いを通して何かを学びたいと一般参加の人たちを含め、総勢104人がキャンプに参加した。
キャンプの一つのキーワードは『PLAY HARD』
PLAYには「(スポーツを)楽しんでやる」という意味がある。
HARDには「懸命に、熱心に」という意味がある。
それを組み合わせて「一生懸命に楽しむ」という意味を持たせているのだ。
日本語には「楽しく」だとか「一生懸命に」という形容動詞の言薬はあるが、実際に動詞として言葉自体が「楽しんでやる」という意味を持つ言葉は存在しない。
「言葉が無いと言うことは、我々日本人にそのような感覚が無いということの証拠なんです」と辻氏。
「楽しんでやる」という感覚を養うために『PLAY HARD』をキーワードに行なわれた今回のサマーキャンプには、ライフスキルも大きなテーマとして掲げ、さまざまな入たちとの交流・コミュニケーションを心がけたたくさんのプログラムが用意されていた。
まず、チームエミネクロスの8月のテーマは「different思考・○△口に気づこう!」だ。
これは、自分の考えや行動が○で、そうで無い人を×と考えるのではなく、世の中には○があれぱ△、口、同じ四角でも◇もあると考える「different思考」を心がけようというもの。キャンプを通してさまざまな人と出会うことで、多種多様な考え方、生き方に触れ合うことができるというメニューだ。
それから「100人で自己紹介!」
これは、先に述べたテーマの一つである“コミュニケーション”を図る上で、まずは相手を知ることから始めようということだ。アメリカで心理学やライフスキルについて学んできた椎名純代さんによるプログラムで、参加者全員による自己紹介ゲームだ。
また、同じく椎名さんのプログラムで「コミュニケーションと新たな発見」に基づいた宝探しゲームも。
他には、車イスB・Bの選手に、障害を負うことになってしまった経緯や車椅子B・Bに出会うまでの話を聞いたり、車椅子B・Bを実際に体験する時間が設けられた。また、「楽しく一生懸命に」をテーマにシューティングコンテストが行なわれたり、ビデオ上映会の時間や、聴覚障害を持つ選手たちとコミュニケーションを取るために、手話の練習をしたりと、息つく暇が無いほど盛りだくさんのメニューが日程に組まれていた。
更には、保護者として参加の大人を対象に大人だけの交流会の時間。
一縦参加のスタッフを対象に、辻氏からコーチカのセミナーと、ディスカッションの時間が設けられた。
このキャンプの特徴約なのは、B・Bの強化にも社会力の育成が必要だと考えていることだ。
子どもたち、大人、障害をもった人たち。年齢やとりまく環境が全く違う人たちが集まり、B・Bを楽しむことを通しながら、コミュニケーションを図ること。これは子どもたちにとって、とても大きな経験となったに違いない。
特に陣害を持った人との接触は、身近に居なければなかなか出来ない経験であり、そのふれ合いから、子どもたちそれぞれが、何かしら感じたことはあったはずである。実際、参加した子どもや保護者からも、キャンプで感じたことや感想がメールや手紙で寄せられており、キャンプは大成功に終わった。
強化・普及が叫ばれている今日のB・B界ではあるが、ただ単にB・B競技の強化と普及を目指す前に、こういった人間形成的な部分での活動も必要なのではないか、と考えさせられた。
Copyright (C) 2000 EMINECROSS
MEDICAL CENTER. All Rights Reserved