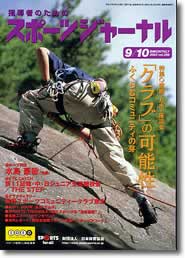 |
||||
 |
 |
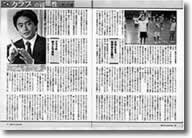 |
 |
 |
|
特 集
|
「クラブ」の可能性
|
●ふくらむ
コミュニティの |
芽
|
座談会
“クラブ”は
からだとこころの
拠りどころ
“クラブ”は
からだとこころの
拠りどころ
橋本聖子氏(参議院議員/スポーツ議員連盟)
辻 秀一氏(エミネクロスメディカルセンター長)
水上博司氏(三重大学教育学部助教授/クラブネッツ)
※司会者
| 資金・運営・人材など様々な面で“クラブ”の立ち上げには困難がつきまとう。それらを乗り越えてなお、われわれの拠点をつくりたい!と、いま全国で、自立した『総合型地域スポーツクラブ』を目指し、情熱を持って夢の実現に邁進する人たちの姿が目につく。スポーツには、それ自体の魅力である「する」「みる」感動と興奮だけでなく、多くの人々の無償のパワーをつなぎ集約していく、さらに大きな可能性が秘められているようだ。“クラブ”はその可能性をひき出すものとしても期待されている。しかも時代の流れが要求する社会的機能=コミュニティ再生をも担いそうである。この問題と深く関わる3人の識者に語り合っていただいた。 | ||
| 地域でスポーツを 共有する環境 |
||
| 水上 各地の総合型地域スポーツクラブの現場を訪れて感じるのは、各クラブのスタッフのみなさんが夢を持って活動に取り組んでいるということです。時間やエネルギー、お金を借しまない、熱意ある人たちによってクラブが維持されているのだということを実感します。それに対して、これは少し厳しい言い方になりますが、行政や自治体、体育振興会、体育協会を含め、既存の地域団体の支援がやや鈍っているのではないか、という印象を持ちました。 「クラブネッツ」の調べによると、日本には1,132のスポーツクラブがあります(※2月1日時点、設立準備中のクラブを含む)。その中には、年間予算1〜2千万円規模で、多くの会員と質の高いコーチ、専従スタッフも抱え、将来はオリンピック選手を育てたい―――そんなクラブもある。 先日訪問した例では、学校の統廃合に伴って廃校になった学校をスポーツクラブの活動拠点として利用できないか、という提案があり、これまでになかった新しい動きとして新鮮だと思いました。 スポーツ振興計画が出て4年目(※平成12年9月に告示)を迎える今、全体の見直しがすすめられる時期(5牟ごと)となってきています。 それでは橋本さんから、総合型のクラブによって生み出されるスポーツの新しい環境、ご自身の選手時代を含めて、今活動されている中で感じていることを率直にお話しください。 橘本 長い現役時代を振り返ってみると、昔と今とではスポーツクラブのかたちは大きく変わってきていると思います。 私が育った小さな町には学校単位の部活動はなかったので地域のスポーツ少年団に入り、小・中学校時代を通して指導を受けました。コーチは元スケート選手の方で、ボランティアで熱心に指導をしていただきました。また、練習への送り迎えなど、家族の協カにも支えられました。 今、感じているのは、昔と比べるとむしろスポーツに親しめる環境が減ってきているのではないかということです。スポーツをまったくやらないか、本格的にやって将来は五輪やプロの選手を目指すか、というような両極に偏っているように思われるのです。 教育者や子供を持つ親のみなさんに話を聞くと、「勉強ができないからスポーツをさせる」という感覚の方が少なくありません。でも、そうではないのだということを理解してもらったり、スポーツは何かということをより多くの人たちに正しく知ってもらうための拠点としての役割りも、総合型地域スポーツクラブに期待しています。 辻 企業スポーツや学校の部活動の現状を見ていると、確かにスポーツのすばらしさを本当に感じとっている人が少ないと思いますね。スポーツは体験であり、スポーツをやっていた人はその体験の中からわかっていることがあると思うのですが、結局、今はスポーツから遠のいていて、見た印象でスポーツをとらえている人が多い。そこで、そのような人たちにもわかるようスポーツのすばらしさを言葉にして伝えよう、と考えました。 私はスポーツドクターをしていますが、選手を診るのではなく、スポーツでドクターがしたい、というのが夢なんです。薬ではなく、スポーツを処方しましょう、と。そのためには、私たちがスポーツのすばらしさを打ち出したときに、スポーツがそれに値するものだというイメージが世の中に広がっていないといけません。しかし残念ながらまだスポーツを処方するというと「根性」「筋肉」といった札が出されるというイメージを持っている人がとても多い(笑)。そこでスポーツの社会的価値とは何かと考えました。そして行き着いたのが、「医療」「芸術」「コミュニケーション」「教育」の4つのキーワードです。「医療」とは、スポーツを通して心身ともに元気になること。「芸術」とは、自已表現、自分を高めたり、まわりの人たちに感動を与えること。「コミュニケーション」とは、あらゆる人たちが友だちになったり、バリアフリーが可能になること。「教育」とは、スポーツを通して成長があること。スポーツ心理学で言うところの「ライフスキル」、私は「社会力」と言っているのですが、それが手に入る。スポーツをしているから仕事や勉強ができる、と。この4つがスポーツのすばらしさの根元なのだと、言葉にしたわけです。 このようにスポーツの社会的価値を言葉にし、スポーツクラブを作っていきたい、という思いから、「エミネクロススポーツワールド」を立ち上げました。そこに参加している子どもたちや親たちには、さきほどの4つのスポーツの価値を享受していますか、といつも問いかけています。また高校生やトップの選手たちには、価値を創造し子どもたちや社会に与えていますか、と問いかけていきたい。「価値」「創造」「享受」をキーワードにしながら、地域の和がもっと広がり、理念、思いを共有する人たちの集合体になると、もっと強い、新しいクラブができるのではないでしょうか。 水上 「医療」「芸術」「コミュニケーション」「教育」という4つのキーワードが挙がりましたが、スポーツの魅カを伝えようとするときに、言葉は本当に大切だと感じますね。 また、理念共有型のスポーツクラブのお話しを聞いて、私の恩師の言葉を思い浮かべました。日本のサッカー史に大きな影響を与えたサッカーコーチのクラマー氏の名言に「サッカーは子どもを大人にし、大人を紳士にする」というものがありますが、私の恩師は「それは“サッカー”ではなく、“クラブ”だろう」と言っていました。クラブという集団の中にある人間関係やコミュニケーション、つまり辻さんの言うところの創造と享受の関係、そういったものが「子どもを大人にし、大人を紳士にするのだ」と。 辻 なるほど。「理念共有型」について補足すると、私は「理念共有型スポーツクラブ、エミネクロススポーツワールド」と呼んでいるんです。子ども、親、トップ選手、障害者など、さまざまな人たちがいるので、それは社会であり、世界、地球だ、という意味で「ワールド」なわけです。この「理念共有型スポーツワールド」の構想は、ピラミッド型ではなく丸型。ピラミッド型だとこぼれ落ちていく人がいる感じがするけれども、丸構造はさまざまな人がどこにでもいて、まさにワールドを作っているわけです。 橋本 全国各地のスポーツクラブや行政を見て回っていると、スポーツに親しんでもらうための環境整備をしている市町村では、医療費も安いという報告もありました。 また先ほどのキーワードの1つ「教育」に関連するのですが、自分自身を高めていこうとする中で、スポーツにつきものの「勝ち負け」を嫌う人と、好む人がいるでしょう。でも、スポーツを突き詰めて考えていくと、最後は「やさしさ」になると思います。私自身はチャンピオンスポーツを目指してきて、いわゆるピラミッド型の中でやってきました。でも最終的には辻さんの言う丸型へ向かっていくと思うんです。 自分自身を高めていくということは、人に勝たなければならないし、負ける人がたくさん出るということです。そうするといつか勝ち続けることが嫌になったり、自分自身がとても苦しくもなる。でも、一生懸命にがんばって、その結果、自分以上にいい成績を出して勝つ人が出てくると、安心する時期が来るんですね。 水上 重味のある言葉ですね。 橋本 それまでは、勝ち続けることしかなかった人間にとって、それ以上にいい成績を挙げ自分よりも上に立つ人がいることに、心からの賞賛をおぼえる。そして、それよりもさらに上を目指して、自分を高めていく、ということはよくあります。 勝負というのは、自分自身を高める、自分を表現するのがスポーツであるけれども、そこまではいけなくても、一生懸命やること自体が地域社会への貢献であったり、やり続けた気持ちというものが自信やいろいろなものにつながって、最後は相手に対するやさしさになっていくと私は思います。 |
||
| 大切になる 指導者の企画力 |
||
| 水上 総合型地域スポーツクラブの理念には、多種目を多世代で、ということがあるのですが、でも実際には、いろいろな種目の選択肢を用意するのは難しい。指導者にとってもわかりにくいことなんです。そこで私が考えているのは、子どもたちが1年間を通して3種目の大会に出られるような仕組みを作ってはどうか、ということです。例えば、春にはバレーボールの大会に出場する。この指止まれ式でチームを作り、大会という目標を目指す。勝ち負けを経て、大会後にチームは解体します。同じように、夏は水泳の大会、冬は駅伝を目指す。これで3シーズン。四季のうち残る1シーズンは休んで読書をして過ごすのもいい。 辻 なるほど。 水上 総合型地域スポーツクラブの「多種目」という特色を生かす方法として、特にジュニア層にはこのように選択肢をたくさん設けてあげて、体ができ上がってから選手個人が専門種目を選んでやっていくのがいいのではないかと思っています。もちろん、ジュニア時代からの英才教育が重要な種目もあるのでしょうけれども。 ただ、いつもはサッカーをやっている子どもが、たまにソフトボールをやったりすると、とても生き生きとした顔をしているんですね。 辻 違う種目に触れることによって、そこで得たものを持ってまた元の種目に戻ってきますよね。 ただ、クラブがいろいろな大会に出場させるとしても、大会を組織している側がまだそういう意識を持っていないんじゃないでしょうか。 水上 その意味ではこれからのクラブの指導者には、大会やリーグ戦を自ら企画する能カが求められると思います。 実際、インターハイに出場するような学校の指導者は、練習会をやったり、数チームを集めてフェスティバル的な合宿を兼ねたリーグ戦をやっているんですね。それが、普段はゲームに出られないような選手にとってチャレンジの場になっている。意欲的な指導者たちは、すでにそういう発想でやっているんですね。 辻 それから、そういった大会では指導者たちの価値づくりもしたほうがいいでしょうね。インターハイで勝つだけではない、別の指標による指導者の価値を、です。 例えば、高校や大学がスカウティングをするとき、あそこのクラブは人間的に優秀な人材を輩出する、といった具合に。スカウティングでは、学校側は選手の競技成績を見るわけですが、そうではなくて、あのクラブのジュニア出身の子どもは人間性が豊かでコミュニケーションも取れて、学業もきっちりできて、主体的に積極的に取り組める、そんな優秀な人材が輩出されるクラブだ、という評価をきちんとする。そうなると、勝たせなければ評価されない、というようなことがなくなります。2つの尺度で指導者の評価があればいいですね。 水上 指導者も評価することによって、子どもだけでなく指導者自身も成長する、と。 橘本 確かに、トップ選手の指導者がようやく表彰されるようになってきましたが、それでもまだよほどメジャーな指導者だけに限られているのが実状です。そして優秀な指導者のもとには必ずいい選手が出てきます。でも本当は金の卵はどこにでもいるのだと思います。あとはそのすばらしさを引き出すことができるかどうか、ということだけですね。素質を持っていて、オリンピックを目指せるかもしれないのに、本人がそれに一生、気が付かないといったことがきっとたくさんある。そういう素質を見つけることができる人と、めぐり会うためにも、自分もやってみたいと思えるような場所づくりが必要ですし、総合型地域スポーツクラブに見抜く目やカがあれば、全体がもっとレベルアップされると思います。 |
||
| クラブの 魅力と可能性 |
||
| 水上 総合型地域スポーツクラブの中央研究班で、クラブづくりの啓発のためのパンフレットを作ったのですが、その際に、陸上の為末大選手にクラブのよさを語ってもらったんです。為末選手は陸上のクラブ育ちで、自分が競技生活を終えた後には、やはり陸上の指導をしてジュニアの子どもたちを育てたいと言っていました。ところが、そういう道はなかなかないし、それで食べていけるようなチャンスがないのが現状です。 その意味では、クラブには大きな魅カがあり、チャンスもある。 ドイツなどでは優秀な選手が引退したあと、ジュニアの指導者として、社会的にかなり高い位置に置かれていますよね。 辻 キャリアトランジション(職業の移行)という点から見てもうまくいっている。 水上 Jリーグではセカンドキャリアに取り組んでいますよね。選手としてのファーストキャリアを終えてピッチを離れたあと、「元Jリーガー」としてどう生活していくか。リーグを挙げて後押ししている。じつはそれが大事なんだということですよね。 橋本 そのあたりは今、私がいるところ(行政)の責任でもありますね。日本では、スポーツの意味をなんとなくはわかっているけれども、そのために何をするかまで明確にはなっていない。 辻 創造している人が、結局は実際にスポーツをやっている選手しかいなくて、その人たちもやらされてやっている人が大半なのでは。橋本さんのように自分でその価値に気づいてロールモデル(望ましい見本)にもなっていこうとする人が少ない。やらされている人が現役を終えたあと、まったく別の仕事をやる、というふうになってしまっている。そうすると、周りの人たちもそういうものだという印象を持ってしまう。 もうひとつあるのはメディアの問題。メディアがスポーツの印象を作ってしまっている。スポーツの本当の価値はいろいろなところに内在しているのだけれども、表層的な勝った負けたや、お涙頂戴的なストーリーだけを作っていく。するとスポーツが何か遠い存在か、根性もので私とは全然違うわね、というふうになってしまう。 でもクラブ化が進むことによって、「スポーツ」という言葉に、今までのようなトップの選手やマスコミを通じて知ったことだけではなく、近所のクラブの中での印象をみんなが持つようになれば、日本のスポーツ観が変わっていくような、そんな期待が持てるように恩います。 水上 世界選手権やオリンピックといった一定の水準までがんばった選手たちの受け皿としてのクラブのあり方。これは、政界や財界、もちろん体協やJOCも含めて、考えていくべき時なのだろうと思います。 Jリーグのヴィッセル神戸に所属していた塚野選手は、神戸を退団したあと故郷の鳥取に帰ってスポーツクラブを作りました。廃業したアイスアリーナの床にカーペット貼ってフットサルのコートにし、昼間は健康体操のクラスを開いたりしています。また、JFLの鳥取FCのマネージメント業務もしたりと、ひとつのビジネスモデルにさえなっている。現役を終えたあとも、こういう生き方があるんじゃないかというメッセージがドンと出れば、ほかの選手たちにとってもいいことですよね。 クラブネッツではホームページを開設しており、中間支援組織として少しずつ頼りにされるようになったかなと思っているのですが、指導者のみなさんから事務局宛てに電子メールでたくさん間い合わせが寄せられます。そうした問い合わせを受けて感じるのが、クラブライフやクラブの文化といった情報が、末端まで行き届いていないということです。では、誰が情報を伝えるのかというと、トップ選手たちがホームページなどを通じてメッセージを送るとパンチがあるんですね。 辻 今のマスコミのやり方だと、みんなに近いロールモデルというよりも、みんなにはできないことをやり遂げたというとらえられ方ですからね。清水選手のように足を太くはできないし、マイケル・ジョーダンのように高くは飛べない、イチロー選手のように速くは走れないし、松井選手のようなパワーはない。だけれども、あなたもライフスキルをスポーツの中で養うことができるんですよ、スポーツのライフスキルはこういうものですよ、ということをメッセージすると、「それなら自分もできるかな」と思う。では、それができる場所はどこかというと、クラブがあなたのすぐ横にあるじゃないですか、と。そういう風になれば、トップ選手と一般の人たちがリンクしていく気がするんですね。 水上 そういう意味でも、先ほどお話しした為末選手には共感しますね。水泳の北嶋選手も、40人くらいの子どもたちに指導している様子が新聞で紹介されていました。メディアを通じてメッセージを発信している。サッカーの中田選手もそうですよね。 彼らのそういうメッセージは、子どもたちにも響いていると思うんです。私が一番感動したのは、イチロー選手の「道具を大事にしましょう」というメッセージです。彼がグローブやシューズを磨いている写真が一緒に掲載されていました。そういうメッセージだけでも、子どもたちに影響を与えています。クラブの影響力も、そういうものだと思うんですよ。 辻 クラブはさらに身近なものですよね。クラブにトップ選手がロールモデルとしていると、遠い存在ではなく、五輪や世界選手権に出場後にまた戻ってきて、話をしたり同じ目線でコミュニケーションする。そんな環境があれば子どもたちも夢が持てるだろうし、自分と同じ部分と違う部分を認識できると恩います。現状では、トップの選手はトップだけでやっていて、両者の間にリンクがない。トップ選手の情報がメディァでしか入ってこない。肉声がない。例えばアメリカのように、イチロー選手が来て「道具を大切にしよう」と言われたら、それこそ一生忘れられないですからね。 水上 そうですね。 辻 そういうことがすごく大事だと思います。アメリカのスポーツ界では社会力がないと勝てない、とスポーツ心理学者が選手たちに教育していますからね。メディアに対してどう受け答えをしたらいいか、メッセージの発し方もトレーニングしている。そこがまだ日本とは違いますよね。とはいえ、日本でもすばらしい選手たちが輩出されてきているから、今こそ変えることができる時期ではないかと思います。 |
||
| クラブに欲しい ロールモデル |
||
| 水上 今僕が構想中のクラブは「多世代」。学年で分けると小学生、中学生、高校生、大学生と、いろいろな年齢の選手がいます。私の持論は、憧れの選手は身近にいる、ということなんです。子どもたちを観察していると、大学生のお兄さんと同じTシャツを着るだけで、けっこうワクワクしているんですね。 辻 本当にそうですね。 水上 だから、清水宏保選手や高橋尚子選手はもちろん子どもたちにとって憧れの選手なんですけれども、じつは私の大学の学生をポンっと連れて行くだけでも「お姉さんのようなスパイクを打ってみたい」とか「お兄さんのようにシュートしたい」とか、真似をしようとする。指導者のみなさんによくお話しするのは、高校生や大学生は、ジュニアの子どもたちにとって憧れの的なんだということ。ぜひそういう機会をたくさん作ってほしいですね。 群馬県の新町スポーツクラブでは、高校生がリーダー会を組織しています。彼らが自分たちで企画し、子どもたちにプログラムを提供している。指導者は少し距離を置いているんです。 辻 高校生リーダーたちの社会カも育ちますね。 水上 そうなんです。だから、スポーツ少年団は小学6年生や中学1,2年生で卒団するのはやめましょう、というのが新町スポーツクラブの理念のひとつとしてあるんです。むしろ、少年団を卒団していくあともクラブと関わりを続けるための選択肢をどんどん増やしてあげよう、ということでやっている。小学生たちは高校生や大学生のお兄さん、お姉さんを見ているので、今後は自分たちがその世代になったときの関わり方として、選択肢を持つことができる。 辻 たくさん与えてもらったから、今度は次の人たちに返してあげるという好循環が生まれますね。まさに、社会としてのモデルですよね。高校生ぐらいでそういうことができたらすばらしいです。 橋本 人に教えることによって、自分がわかることになりますからね。 辻 今の高校生は、まあ大学生もそうかもしれませんが、自分で考えることがあまりなくて、言われたことだけ練習しているという学生がとても多い。でも今お聞きしたような関わり合いがあれば、もっと創造性のある選手が増えるかもしれませんね。 水上 そういう意味ではクラブというのは、将来のスポーツ界を支える人材を輩出するルーツだと思うんです。その可能性を期待したいです。 辻 そうですね。 水上 クラブは学校と違って、小学生の子どもたちと一緒に、中学生や高校生もいる。こういう関係性の中で、得られるものはたくさんあると思うんです。 橘本 クラブの活動を通じて得た経験が学校にとってもいい影響を及ぼすことも考えられますよね。 辻 多世代交流の場としては、私のクラブでは小学生からトップの選手までを入り混ぜた、縦割りの練習日というのを時々設けています。身長が2メートルぐらいあってダンクシュートをバシバシ決めるような選手と小中学生や車椅子のメンバーとで一緒に試合をしたりするわけです。みなで助け合いながらやることになるので、例えば小学生と中学生との関係もよくなるし、トップチームの試合があるとたくさんの人が応援に来てくれるわけです。 水上 まさにクラブらしいですね。 辻 昔は公園に行くと、のび太君やジャイアンがいて、いろいろな人間がそこで遊ぶことで社会カが生まれていたと思うんですよね。今はそういう場がなかなかないけれど、スポーツだから、クラブだから、そういうことを教えてあげられるんじゃないかと思います。私はクラブこそが地球を救えるんじゃないかという気でやっていますよ(笑)。 |
||
| 課題の 克服へ向けて |
||
| 水上 今クラブが抱えている課題を挙げていきますと、まずお金がない。それと人(指導者)の問題。運営のスキルや場所の問題。それから情報(啓発)の問題等があると思います。最後に、こうした問題を踏まえてご意見をうかがいたい。 橋本 私はクラブは人づくりの場だと思っています。もちろん子どもたちだけの場ではありませんが、豊かな人間性を持った人に育てることが一番の目的だと、個人的には考えています。そのためにも地域に根ざしたクラブが住民に頼られる場所になっていかなければならないし、そういうカをつけていかなければいけないと思っています。「あのクラブに行けば何かを得られるんだ」という場になることが理想ですね。 水上 欧米に行くと、クラブがなくなってもらっては困るという存在になっていることを実感します。ある意味、阪神ファンにとってのタイガースみたいなものですね。日本ではまだクラブがそういうものにはなっていない。 学校運動部なり企業の運動部が日本の競技カを支えてきたという歴史があるので、「総合型地域スポーツクラブ」という新しい名前を掲げていると、常連さんが警戒してしまうということもあるようです。 辻 人やお金や場所の問題というのは、どんなことをやってもつきまとう問題ですよね。私も実際にクラブを運営していく中で、困っているのは確かですし、そう簡単に解決できるものでもないのでしょう。だからこそ私は理念というものを大切にしたいんです。根幹にそういうものがあればそれぞれの役割を担う人間が集まってくるだろうし、育つんだろうと思います。中にはスポーツはできないし、しないけれど、理念に共感して運営面でカを発揮してくれる人もいるでしょう。さまざまな人々をつなぎ止める接着剤になるような理念を各クラブが明確に打ち出していけば、さまざまな問題も少しずつ解決していくんじゃないかと思っています。 水上 私は岸和田の山直スポーツクラブというところにずっと調査に入っていて、一緒にクラブづくりをしてきました。当初、体育館の一角の空き倉庫にクラブハウスを作って、電話とファックスと冷蔵庫を置き、事務職員を雇いたいと言ったところ、学校や行政側から「なんでスポーツするのにファックスがいるのか」ととらえられてしまったのです。こうした理解はなかなか一般的には得られていないんだと思うんですよ。でもこれらはクラブの権利だと思います。 辻 それじゃあ市役所に電話を置いてはいけないと言っているのと同じようなことですよね。クラブも、市役所のように地域に根ざした社会的な価値があるとアイデンティファイできれぱ、クラブの権利も当たり前のものとして認知されるはずですよね。 水上 ただ、財源を供給する側からすれば、きちんとした規律を持ち、自己決定していないような団体には出せないということになるでしょうね。 辻 そのためにも創造と享受というものが明確になっていないといけない。それがなく数名の人たちの自己満足に終わってしまわないためにも、享受している人が多くなってよりクラブの価値も認められるんじゃないかと思います。 |
||
Copyright (C) 2000 EMINECROSS
MEDICAL CENTER. All Rights Reserved